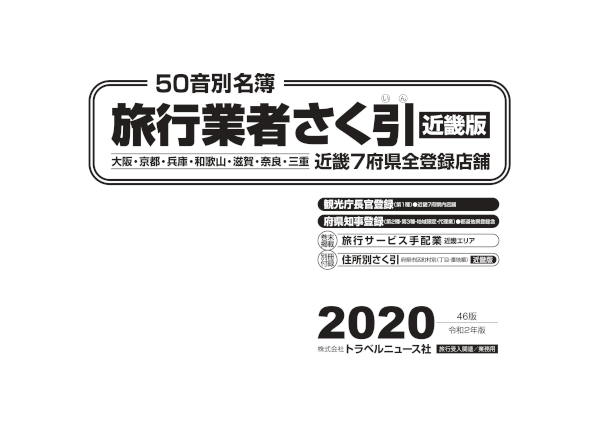奥能登の今を訪ねて(1) 被災地の現状と観光の可能性
今年5月、奥能登の被災地を一周した。令和6年能登半島地震から約1年半、能登町出身で元金沢大学特任教授の宇野文夫さんとともに現地の今を実際に見て回る中で、復旧の現状と観光の可能性について多くの示唆を得た。(トラベルニュース社まちづくり観光研究所シニア研究員・釼菱英明)
○
同行していただいた宇野さんは、私が日本旅行に勤務していたころ「国立大学金沢大学シニア短期留学2007年度・14日間プログラム」の金沢大学の担当者として出会った。その後、08年から15年にかけて延べ6回、金沢だけでなく能登を訪ねるプログラムをともに実施してきた間柄だ。今回も快く引き受けてくださった。
滞在先の金沢東急ホテルで宇野さんと落ち合い「能登里山海道」を北上。途中、千里浜なぎさドライブウェイに立ち寄り、海岸沿いの砂浜を走行した。一部で海岸線の変化を感じたが、以前と変わらずロマンチックで美しい眺めだった。能登空港を越えるあたりからは山肌の崩落が目立ち、道中は急なアップダウンや左右へのハンドル操作が続き、慣れていないと運転が難しいと感じた。
輪島市では、名物の「朝市」会場が更地となっていた。周辺では264棟が失われ、16人が亡くなられた。道路を塞いでいた建物は公費で解体されたという。朝市の女性たちは、近くの「スーパー・パワーシティ輪島ワイプラザ」で“出張朝市”を再開し、移転先が決まるまで全国各地への出張販売なども精力的に展開している。被災者のたくましさが光る。ぜひ応援したい。

スーパーマーケット内で出張朝市として再開
続いて、市内を流れる塚田川へ。昨年9月の豪雨で家屋が流され、中学3年生の遺体が福井沖で見つかったと報道された場所だ。川幅が細く、驚くほど浅い川であった。
その後、震災前は美しい景観を誇った「白米千枚田」へ。1004枚の棚田は崩落したが、昨年は120枚、今年は250枚で田植えが行われたという。
珠洲市の道の駅「すずなり館」横の「すずなり食堂」で昼食。「タコカツ丼」を頼んだ。絶品だった。腹が満たされ、気持ちがほぐれて明るくなった。この食堂を立ち上げたのは、シニア短期留学プログラムでお世話になった「典座(てんぞ)」の坂本信子さんで、被災した珠洲市の料理人たちが地域再生の一翼を担う。坂本さんとはお休みで会えなかったのが残念だったが、地域の絆が生んだ小さな復興モデルだ。
珠洲市の「見附島」へ。軍艦島と呼ばれる観光名所も崩落し、風景が一変していた。近くに建てられた木造の仮設住宅は、建築家・坂茂さんと珠洲市が契約し実現したもので、明るく住み心地の良さを感じさせた。

かつての風景とは一変した見附島(軍艦島)
帰路、マルガジェラート能登本店でいただいたジェラートは、疲れた心に優しく染み入った。
(次の記事)奥能登の今を訪ねて(2) 新たな景観と文化財再建の課題
- 修旅目的地の魅力 長野県学習旅行誘致推進協、近畿圏の中学校教諭ら招く(25/10/31)
- 旅行の価値は良質な「眠り」にあり 楽天がビジネスイベント、睡眠が作る満足度を提言(25/09/03)
- 最新データとトレンド じゃらんリサーチセンター、観光振興セミナー開催(25/09/02)
- 奥能登の今を訪ねて(2) 新たな景観と文化財再建の課題(25/08/04)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(2) テーマは「永遠」2千年前の石など展示/イスラエル(25/05/30)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(1) 観光名誉広報大使に坂口健太郎さん/韓国(25/05/30)
- 関空、国際線強化で受入整備 第1ターミナル大規模改修完了(25/04/01)