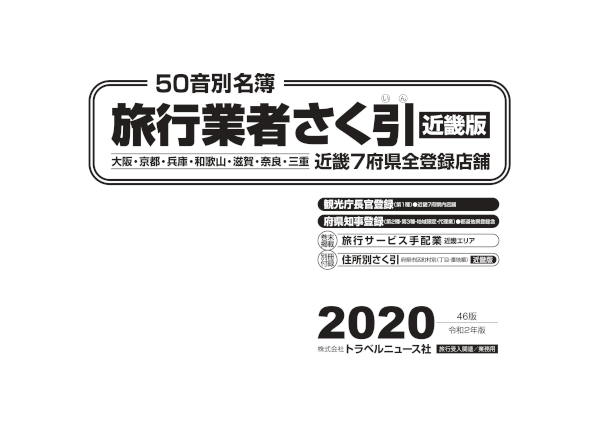奥能登の今を訪ねて(2) 新たな景観と文化財再建の課題
「ダークツーリズム」の希望
千枚田から国道249号線「奥能登絶景海道」を北上すると、地震により従来の国道やトンネルは使えなくなり、隆起した海岸線に新しい生活道路が出現していた。崩壊した逢坂トンネルを越えたところでUターンしたが、海側から見た風景は、まさに「3千年に一度の震災」によって生まれた新しい景観だった。かつてトンネルがあった時には見ることができなかった海の風景。そのスケールと迫力に、ただただ息をのんだ。地域が復興すれば、必ずや大きな観光資源になると確信した瞬間だった。
後日テレビで、国土交通省や石川県、該当の市町村が検討会を開き、隆起した海岸線を新たな「絶景」として観光ルートに組み込む方などの方針を報じていた。

震災で生じた新たな海岸の景観
国の重要文化財「上時国家(かみときくにけ)住宅」は過去幾度となく訪れていたが、運営困難を理由に一般公開は23年9月に終了していた。文化財指定の際には「近世木造民家の一つの到達点」と評されていた。
時国家は平安時代末期、平家が敗れ能登に流刑となった平時忠を祖とし、江戸時代には天領の大庄屋を務め、名字帯刀を許された家系。
地震と豪雨で優美な姿を残していた母屋の柱が倒れ、2階部分が崩落し、泥が入り込んでいる。第25代当主・時国健太郎さんは「何年かかっても再建したい」と語り、復旧の遅延や費用負担、相続など多くの不安を抱えながら文化財の再建に取り組んでいる。
このように震災や豪雨で被害を受けた多くの文化財もこれから再建に向け本格的に動き出すことになる。復旧には長い年月がかかるが維持保存・活用していくためにツーリズムがどう貢献できるかも大きな課題となる。
宇野さんとの会話で話題に出たのが「ダークツーリズム」。
輪島では朝市跡などで、欧米人の旅行者が静かに手を合わせ、祈りを捧げる姿が幾度となく目撃されている。彼らはガイドもつけず、おしゃべりもせず、静かに現場を後にする。多くがレンタカーで訪れ、宇野さんが見かけたグループは名古屋ナンバーだったそうだ。金沢観光のついでか、意図的な訪問かは分からない。
仙台の「語り部タクシー」や福島県の「ホープツーリズム」に見られるように、記憶をつなぐためには、震災遺構の保存や「語り部」の育成を含め、教訓を未来へつないでいく構えが能登でも必要だ。
能登半島は震災から1年半近く経った今も、現地ではボランティアや復興関係者への宿泊提供が優先され、調査で入りたい金沢大学の学生すら宿が確保できない状況だ。当面は、金沢からの日帰り訪問が現実的だろう。
だが、震災を経験した地域こそ、観光を通じた支援が復興の力となる。施設の再建、文化の継承、地域の再評価、そのすべてに観光の力が関与しうる。災害の多い日本だからこそ、被災地支援としての観光のあり方に新たな視点が求められているのではないだろうか。
その後、ダークツーリズムに関する研究会に参加された宇野さんは「機会があれば現地を案内したい」とおっしゃっていた。今回の現地視察を通じ、復興の道のりは遠くとも、そこに確かな希望と可能性があることを実感した。案内をしてくださった宇野さんに深く感謝するとともに、今後も能登の姿を伝え続けていきたい。
(前の記事)奥能登の今を訪ねて(1) 被災地の現状と観光の可能性
- 修旅目的地の魅力 長野県学習旅行誘致推進協、近畿圏の中学校教諭ら招く(25/10/31)
- 旅行の価値は良質な「眠り」にあり 楽天がビジネスイベント、睡眠が作る満足度を提言(25/09/03)
- 最新データとトレンド じゃらんリサーチセンター、観光振興セミナー開催(25/09/02)
- 奥能登の今を訪ねて(1) 被災地の現状と観光の可能性(25/08/04)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(2) テーマは「永遠」2千年前の石など展示/イスラエル(25/05/30)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(1) 観光名誉広報大使に坂口健太郎さん/韓国(25/05/30)
- 関空、国際線強化で受入整備 第1ターミナル大規模改修完了(25/04/01)