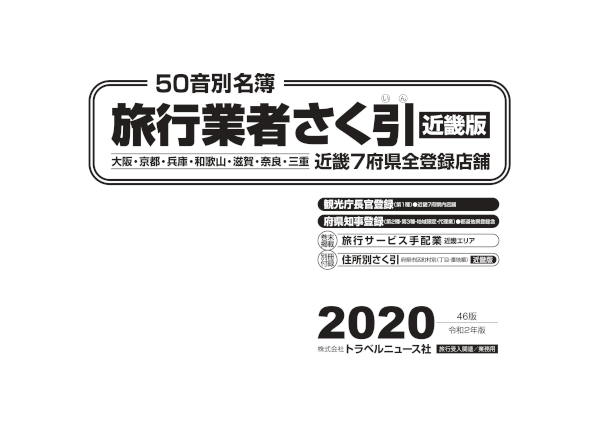障害の「社会モデル」−聞こえない−(2)
19/10/15
前回は、聴覚障害者が宿泊施設を利用する際の困りごとを考えてみました。
宿泊施設を利用する際に、「聞こえないので、フロントスタッフの説明が理解できない」。この「○○できない」ことの原因を「聞こえない」という心身機能に障害があるとする考え方を「医学モデル」といい、スタッフの説明が分からないのは、情報提供が音声による提供だけであったことに原因があり、施設利用者全員が「聞こえる」ことを前提にした対話の準備しかされていないことに問題があります。これを「障害の社会モデル」といいます。
今回は、宿泊中に緊急事態が発生!聴覚障害者に緊急情報を周知していただくために事業者としてとるべき責任は何か?を考えます。
まず考えていただきたいことは、宿泊施設を利用するのはどんな方?という想像からです。実に多様ですね。
ダイバーシティと捉えるべきでしょうか。老若男女、障害の有無も含め人間には個性や特性があります。聴覚障害といっても聞こえ方は様々です…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2019年10月10日号)
続きをご覧になりたい方は本紙をご購読ください
共創の旅―サービス介助士日誌 の新着記事
- インクルーシブ・コミュニケーターとは?(25/12/16)
- 新たなジェロントロジーの定義と宣誓(25/11/18)
- ジェロントロジーを学び考察(25/10/17)
- ジェロントロジー総合会議@万博(25/09/18)
- 万博テーマとジェロントロジーとの共通点(25/07/17)
- お客様から教わった「おもてなし」(25/06/16)
- 万博の未来社会PJと熱中症対策(25/05/16)