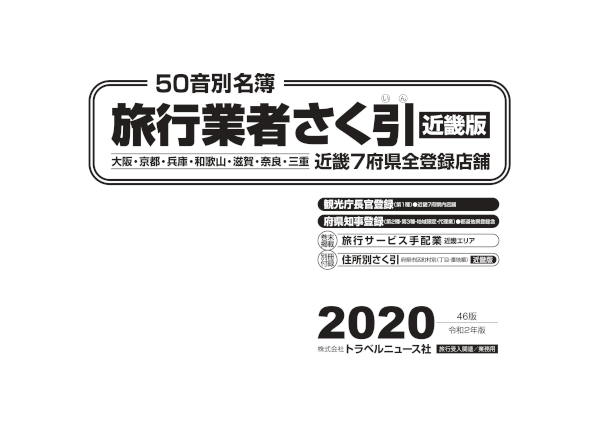人口減に対応する地域経営―日本版DMOに必要な視座 和歌山大学がシンポジウム(1)
「国際的視野で考える日本・関西インバウンドの次なる展開」と題したシンポジウムが5月16日、和歌山大学国際観光学研究センター(加藤久美センター長=和歌山大学観光学部教授)の主催で開かれた。大阪市内の会場には、関西をはじめ各地のDMO担当者ら100人を超える参加者が出席し関心の高さをうかがわせた。
はじめに4氏が基調講演。口火を切った世界観光機関(UNWTO)のパトリシア・カルモナさんは、2018年の世界の旅行人口(到着ベース)が前年比6%増の14億人に達し、30年の目標18億人は楽に超えるとの見通しを示した。その上で「日本は20%増で急成長しています。今後20年に4千万人というチャレンジングなターゲットを達成するためには、競争優位性と持続可能性の両立が不可欠です」と指摘。プロモーションとマーケティングだけの地域経営から、包括的な取り組みが必要と話した。
田辺市熊野ツーリストビューローの多田稔子会長は、世界遺産登録でドッと押し寄せた観光客に疲弊した地域観光からの脱却の取り組みを紹介した。「民間組織の強み、行政的な平等主義ではなく資源の絞り込みをしていきました。ターゲットは外国人とし、サインのローマ字表記を統一、温泉はホットスプリングとかスパではなく『Onsen』にしました。英語以外の表記はあきらめました」などと一本筋の通った受け入れ態勢の整備を行った。
「初めて来る人に一遍上人と時宗の話をプロモーションしても伝わるわけはありません。必要な情報は観光情報ではなく、泊まる、移動、食べるです。でも、歩く仕組みがないのにプロモーションをしても意味がない。そこで着地型旅行会社を設立したのです」
設立したDMC「熊野トラベル」は18年、4億5千万円の売上があり、その8割は地域に循環させることにつながったという。その結果、ビューローの目標だった「地域の人たちが笑顔で暮らせること」に寄与できたと多田さんは自負した。
(次の記事)人口減に対応する地域経営―日本版DMOに必要な視座 和歌山大学がシンポジウム(2)
- 修旅目的地の魅力 長野県学習旅行誘致推進協、近畿圏の中学校教諭ら招く(25/10/31)
- 旅行の価値は良質な「眠り」にあり 楽天がビジネスイベント、睡眠が作る満足度を提言(25/09/03)
- 最新データとトレンド じゃらんリサーチセンター、観光振興セミナー開催(25/09/02)
- 奥能登の今を訪ねて(2) 新たな景観と文化財再建の課題(25/08/04)
- 奥能登の今を訪ねて(1) 被災地の現状と観光の可能性(25/08/04)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(2) テーマは「永遠」2千年前の石など展示/イスラエル(25/05/30)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(1) 観光名誉広報大使に坂口健太郎さん/韓国(25/05/30)