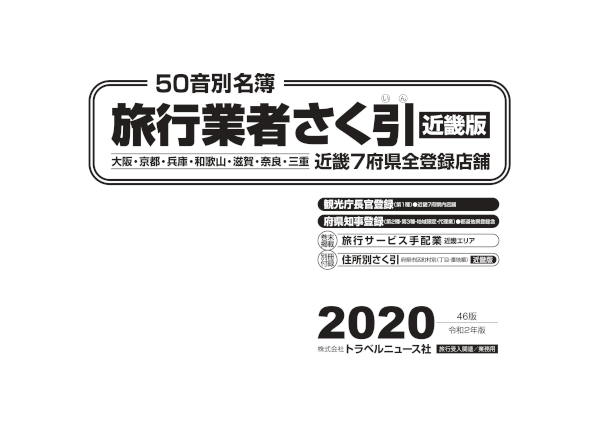サービス介助士だから気づく防災の視点
緊急事態宣言が一部前倒しで解除されましたが、まだ安心はできません。新型コロナウイルス発生から1年が過ぎ、私たちは何を学んだのでしょう。
1.マスクの着用と手洗いの徹底
2.3密回避
3.ソーシャルディスタンス
この3つにプラスして、「責任」という言葉が加わったのではないでしょうか。無症状という感染もあり、どこで感染するのかわからないことへの不安。感染拡大防止のため外出自粛、そして『STAY HOME』という言葉。どれも私たちの責任ある行動が求められます。自分の感染を防ぐだけでなく、人にも感染させないという「責任」が求められます。
もう一点、3月11日は東日本大震災から10年です。ここでも私たちはちゃんと学びを生かせているのでしょうか。今回はサービス介助士の視点から防災も見ていきたいと思います。
超高齢社会の到来、多様性への理解の高まりを受けて「バリアフリー」や「ユニバーサルデザイン」という言葉は当たり前となりました。災害などの非常時においては平常時以上に高齢者や障害者への配慮が必要です。混乱した状況の中で最も支援が必要な方への対応が行き届かずに、被害が広がってしまうことがないようにしなければならない…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2021年3月10日号)
- 中学生が考える共生社会(26/02/18)
- インクルーシブ・コミュニケーターとは?(25/12/16)
- 新たなジェロントロジーの定義と宣誓(25/11/18)
- ジェロントロジーを学び考察(25/10/17)
- ジェロントロジー総合会議@万博(25/09/18)
- 万博テーマとジェロントロジーとの共通点(25/07/17)
- お客様から教わった「おもてなし」(25/06/16)