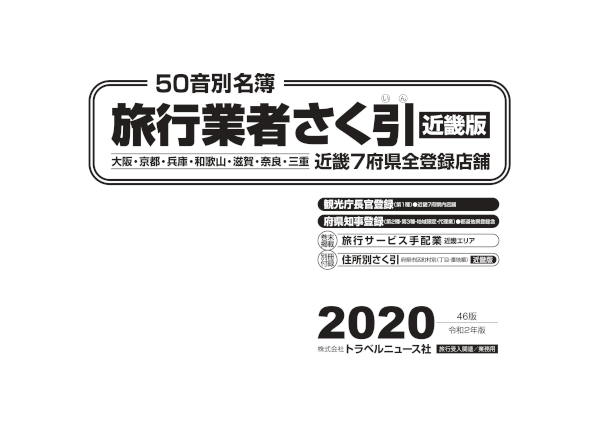認知症の発症と「難聴」の関係
今、皆さんのパソコンやスマートフォン、またテレビの音量はどうなっていますか? 最大限になっていませんか? 耳を守るための適正音量は、機器が出せる音量の半分以下と言われています。
さて、近ごろ耳の聞こえが悪くなったと感じることがあるなら、認知症の初期症状の可能性もあり、改善が必要かもしれません。生活習慣を改善することで認知症の発症リスクを下げることは前回もお伝えしました。そして予防可能な認知症発症リスクの中でも影響力が高いものに「難聴」があります。耳の聞こえが認知機能に大きな影響を与えているのだとすれば、難聴を予防することは、認知症予防の中でも効果の高い方法であると言えます。
まずは、「難聴」についてです。「難聴」とは、音が聞こえにくくなる状態の総称ですが、聞こえにくくなる原因は様々で、耳そのものや神経、脳の異常などがあります。特に内耳から聴神経に何らかの障害が発生することで起こる難聴が一番多いとされており、感音性難聴と呼んでいます。
年齢を重ねることによって誰にでも起こる可能性のあるもので、加齢により起こる難聴を老人性難聴と言います。聞こえにくいことと認知症の関係を想像してみましょう。聞こえにくくなると、相手の話が分かりにくくなり、毎回聞き返していると相手に嫌がられるのではないかという不安から聞き流すようになる。これが続くと…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2023年10月10日号)
- インクルーシブ・コミュニケーターとは?(25/12/16)
- 新たなジェロントロジーの定義と宣誓(25/11/18)
- ジェロントロジーを学び考察(25/10/17)
- ジェロントロジー総合会議@万博(25/09/18)
- 万博テーマとジェロントロジーとの共通点(25/07/17)
- お客様から教わった「おもてなし」(25/06/16)
- 万博の未来社会PJと熱中症対策(25/05/16)