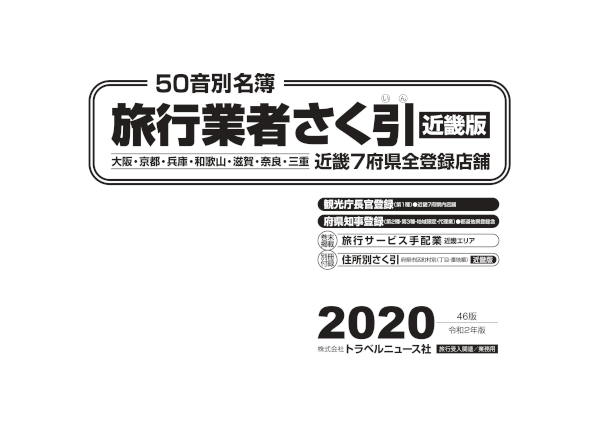訪日客への医療対応 東京観光財団が専門家招きセミナー(1) 患者・医療機関・観光事業者三者に不安多く
訪日外国人旅行者のケガや病気に、医療の現場はどのように対応しているのか、どんな課題があり、国はどのような対策を取ろうとしているのか−。東京観光財団(TCVB)は2月27日、「訪日旅行者の安全確保に向けた取り組み」をテーマに第13回「TCVBミーティング」を開いた。訪日旅行者の緊急医療対応について、国が構築しようとしている制度や、訪日客の身近にあるホテルや旅行会社、観光協会といったエリア事業者に何が求められているかについて専門家から聞いた。
「医療機関が旅行者の患者に慣れていない」
講師として話したのは国際医療福祉大学大学院の岡村世里奈准教授。訪日外国人旅行者の医療対応について(1)現状と背景にある問題点(2)国の取り組み(3)観光関連事業者にできること―について整理して紹介した。
まず、訪日客が急増する前後で医療機関と外国人患者の関係は大きく変わっていることがある。
「従来、外国人患者は在日外国人が主で、日本の公的医療保険に加入しているし、日本語のコミュニケーションも本人や家族、友人などを通じてできます。こうした点で日本人と区別がなかった」

岡村准教授
つまり、多くの医療機関が旅行者の患者に慣れていないのだという。しかし、訪日旅行者のケガや病気の患者は緊急性が高い傾向があり、いつ、どこで、どのような状態・言語の患者が受診するかは予測困難で、慣れていない医療機関でも関与せざるを得ない現状がある。
その上、医療文化や医療制度が国によって大きく異なるという問題もある。日本の医療従事者は外国の医療習慣を知らないし、外国人患者も日本の医療習慣・制度を知らない。
「例えば医療機関での受付から受診までの流れが違います。海外では前払いやカルテを患者本人が保管する国もあります。患者は自己負担がどのくらいになるか分からず不安ですし、異なる医療費請求の事務は医療機関の負担にもなります」
訪日旅行者の患者に見られる特徴と、医療対応の現状についても注意を払う必要がある。
「医療機関を見つけることが困難だったり、医療費の心配などから悪化してから受診するケース、大病院志向の強いアジアなどからの旅行者は、軽症であっても総合病院を受診したがる傾向があります」
一方、患者から真っ先に相談を受けるホテルや旅行会社などの観光事業者も、言語や医療に関する知識・情報の欠如から適切な対応ができない、医療機関から受け入れを断られるなど対応に苦慮している。それだけでなく、医療機関への医療費支払いの代行や紹介責任を迫られることもある。
(トラベルニュースat 19年3月10日号)
(次の記事)訪日客への医療対応 東京観光財団が専門家招きセミナー(2) 保険加入促進や多言語案内を
- 訪日4千万人時代 村田観光庁長官、地域分散へ改めて意欲(26/02/13)
- 26年は「変革の年」 JATA新春会見(26/01/26)
- 四字熟語で2026年の観光を占う 5氏とAIが選んだ“観字”(26/01/05)
- 万国との交流元年 25年の紙面、世相から(25/12/12)
- 北の大地で紡ぐご縁 北海道旅行業協同組合、受入・送客各80社で商談会(25/11/27)
- クルーズ人口2030年100万人へ 日本クルーズ&フェリー学会が総会・講演会(25/11/13)
- 全旅グローバルペイ始動 旅館ホテル向け全旅クーポン・インバウンド版(25/10/28)