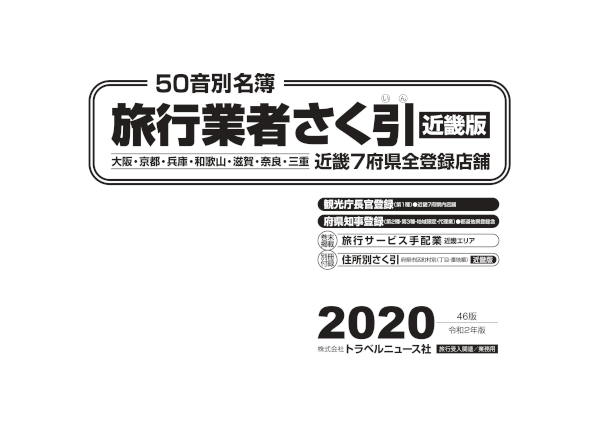観光が日本の自給率を高める
旅行の県民割と地域ブロック割が5月まで続いています。ただ地域内需要はどうしても単価が低めで週末1泊型を招きやすく、全国型のGo Toのほうが交通機関にも波及効果も出て経済効果は高いのですが、7月の参議院選挙をにらみ、政権も風評リスクを想定してキャンペーンに手が出せないのでしょうか。ともあれ6月にはGo Toを再開し、地方活性化につなげ、観光事業者の2年間分の負債を埋めていかなくてはなりません。
とりわけ観光事業者が支える地方は、エネルギーや食料の供給源。輸入に依存する都市の人々にとってなくてはならない経済圏です。ウクライナ情勢を見ていてもわかるように、世界の生産人口が減少に転じた今、グローバルが反転し始め、資源・食料・人材の自給率を上げていくことが安全保障につながる時代へと入りました。その時、地方の重要さが今以上に認識されるようになることでしょう。都市在住の給与所得者はGo Toを短絡的に批判しないことです。
一方、地方では、これまで50年間の余暇需要を支えてきた事業者の運営者交替をよく聞くようになりました。倒産しては元も子もありません。運営者が替わることで設備投資がなされ、新たな需要へと舵を切れるのであれば、それは健全な変化であると思います。
地方の新たな需要とは、高齢者の長期滞在、企業のサテライトオフィス、学校のサテライトキャンパスなど、都市住民をベースとした多地域居住・勤務を具現化し、その長期宿泊を獲得するようなものが一例です…
(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)
(トラベルニュースat 2022年4月25日号)
- クマ被害と不安を増幅する私たち(26/01/27)
- 「不安」を旅行需要に転換(26/01/06)
- 同調圧力のない面倒な旅のススメ(25/12/01)
- リアルな救いの場づくりが役目(25/10/29)
- 代打・菅澤“若者よ地球で遊べ”(25/09/29)
- 60の壁と知恵と「怪獣の花唄」(25/09/01)
- マルハラで病むなら旅に出よう(25/07/29)