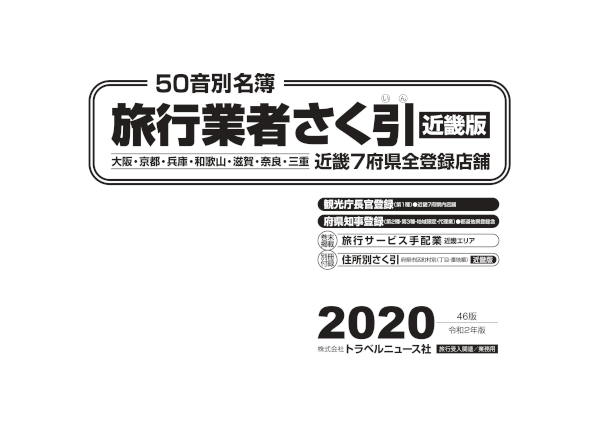脱・さす旧が元気な地域の源泉
さす九というネットスラングがSNSで話題になっています。「さすが九州」の略語で、男尊女卑と思われる出来事があると、未だに男性優位が残っている九州人だからではないかと疑われ、もしそうであれば「さす九だね」と陰で男性が批判される様子を表しています。
鹿児島県出身の学生に聞くと、上の世代では残っていると言います。必ずしも九州に限ったことではないと思うのですが、もし九州に残っているとすれば、薩長が企てた明治維新において定められ、今でも家族の規範となってしまっている明治民法の男尊女卑意識が残っているのかもしれません。
ジェンダー指数が先進国で最低レベルの日本では、未だに結婚すると改姓が求められる、世界で数少ない男子直系家族制が制度の根幹にあります。高校生になると家を出る核家族制ではないので、結婚しても同じ屋根の下で同居し、資産も死ぬまで渡されません。この構造では若い世代は育たず男性老人支配が続きます。
それゆえ、男女平等と口では言いながら、働く世界でも時間給ベースの給与制度を変えようとしません。能力やスキルではなく働いた時間が基準である限り、出産のある女性は永遠に男性を上回れません。さす九ではなく、「さす日」(さすが日本)と言った方が当てはまるような気がします。結果として女性は子どもを産むことができず、国家が衰退に向かっていることを茹でがえるの私たちは認識できているでしょうか。
これは以前から感じていることですが、元気な観光地の多くは、若手の女性たちが前面に立ち、男性が支える構造になっています…
(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)
(トラベルニュースat 2025年5月25日号)
- 「不安」を旅行需要に転換(26/01/06)
- 同調圧力のない面倒な旅のススメ(25/12/01)
- リアルな救いの場づくりが役目(25/10/29)
- 代打・菅澤“若者よ地球で遊べ”(25/09/29)
- 60の壁と知恵と「怪獣の花唄」(25/09/01)
- マルハラで病むなら旅に出よう(25/07/29)
- 生成AIにできない雑談の創造力(25/06/26)