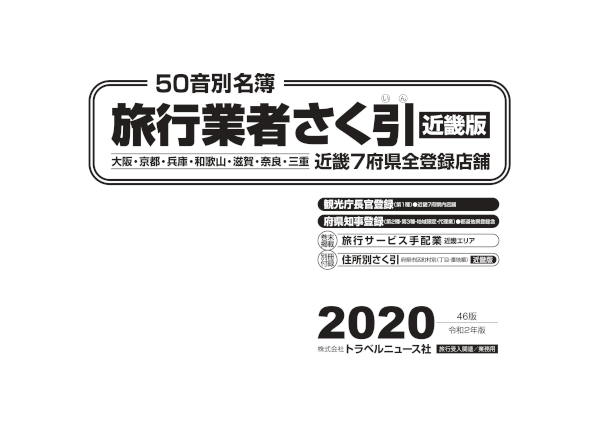「サービス介助士ジュニア」
2008年に初版「サービス介助士ジュニア」を発行し、中学・高校・各種支援学校で導入いただいておりますが、今回初めて大きな改訂を行いました。家族・友だち・地域の人など、日常生活や学校生活で関わる人に対する「おもてなしの心」と「基礎的な介助技術」を身につけた、高齢社会に必要とされるジュニア・ケアフィッターを目指します。
核家族化が進み、日常生活の中で高齢者と接する機会が減っている子どもたちが、高齢者への理解を深め「地域社会で共に生きること」や「より良い社会をつくる」ことを考える。「障害」についても同様に、障害って何だろう、障害はどこにあるのだろう? 社会には、さまざまな人たちが暮らしているからこそ「違い」があって当たり前、同じじゃなくて当然なのです。
次は、この「困りごと」の原因って何? もしかしたら身体に障害があることで困りごとが生まれるのではなく、社会や社会にいる人々によって「困りごと」が作り出されているのかもしれない。障害のある人にとって生活しにくい環境があり、困りごとを生む「バリア」が存在しているのかもしれない、と考えてもらいたいです。
また「死」について考えています。「死」について考えることから「生きる」ことの意味を見つける。「生きる」って何だろう。「いのち」って何だろう。一日一日を大切に、「いかに生きるか」を考えていく。さまざまな人が生活する中でお互いの理解を深め、コミュニケーションをとることが「心のバリアフリー」の実践です…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2022年6月10日号)
- インクルーシブ・コミュニケーターとは?(25/12/16)
- 新たなジェロントロジーの定義と宣誓(25/11/18)
- ジェロントロジーを学び考察(25/10/17)
- ジェロントロジー総合会議@万博(25/09/18)
- 万博テーマとジェロントロジーとの共通点(25/07/17)
- お客様から教わった「おもてなし」(25/06/16)
- 万博の未来社会PJと熱中症対策(25/05/16)