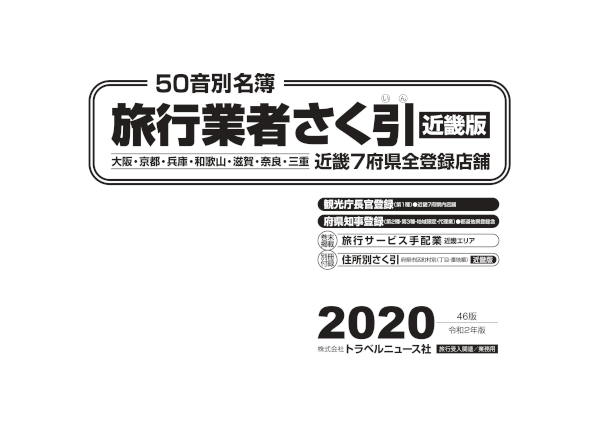特別編・隠岐・海士町へ行く-島の高校生に驚愕し感心
「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」が出した中間とりまとめの解説を楽しみにしている読書の方々にはたいへん申しわけないのですが、今回も前回と同じくDMOとは関係のない話題になります。
今月6、7日の2日間、観光庁田端長官とともに隠岐諸島を訪ねました。海士町が7日に主催した「島の観光会議〜地域におけるこれからの観光の役割とは〜」に田端長官と私が講演講師とパネルディスカッションのパネラーとして招かれたのです。
その前日の6日は西ノ島町を視察した後、午後から海士町の学習センターで「未来を担う島民との意見交換会」に参加しました。役場や関係者から観光に関わる様々な報告を聞かせていただいたのですが、地域振興のお手本と言われる海士町が長年にわたって取り組んできた活動とその実績はどれもこれも他地域のロールモデルとなるようなものばかりでした。
数々の事例紹介の中でも最も素晴らしかったのが、隠岐島前高等学校ヒトツナギ部に所属している現役高校生からの発表でした。特に10年前にスタートした「観光甲子園」で初代グランプリを獲得した時から現在まで続いている交流事業については、地道な取り組みではありますが、生徒が入れ替わっているにも関わらず内容が進歩・進化していることに驚愕しただけでなく、プレゼン自体も大学生と比べても負けないぐらいの質と堂々とした態度に感心してしまいました…
(山田桂一郎=まちづくり観光研究所主席研究員)
(トラベルニュースat 2019年7月25日号)
- 26年の訪日客予測 質の向上へ転換する好機(26/01/30)
- 過去最多の訪日客 “量”の重視から政策再設計を(26/01/09)
- 台湾有事発言 民間交流こそ観光立国の礎(25/12/04)
- 日本の食を守る 観光基軸に「地産地消の経済圏」(25/11/04)
- 中小旅行会社 米国モデルにアドバイザー化(25/10/02)
- 海外予約サイト問題 “安さ”から持続可能へ試金石(25/09/04)
- 真の観光立国とは(25/08/01)