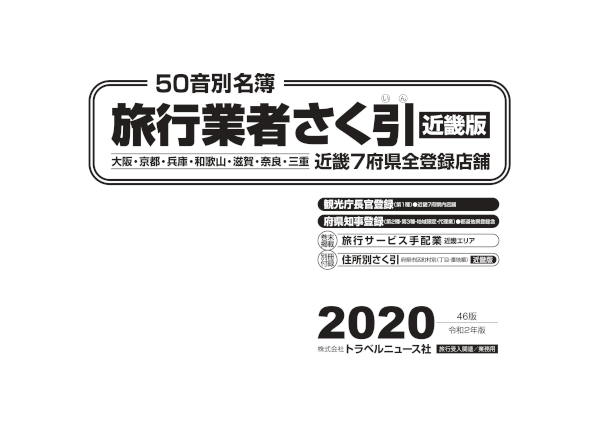手仕事の観光業に誇りを
明治から大正、昭和にかけて日本経済をけん引した絹産業のドキュメント映画「シルク時空(とき)をこえて」(熊谷友幸監督)を見た。
映画は、日本有数の巨大製糸家を輩出した信州岡谷、小説「野麦峠」で知られる製糸工女のふるさと・飛騨古川のほか、米国マンチェスターやフランスのリヨンにまで足を運び、絹に携った各地の人々を撮影した貴重な記録になっている。
ナイロンなど合成繊維が席巻するまで、日本はもとより欧米でも基幹産業だった製糸業。この映画では日仏、日米で互いの人と人とのつながりで製糸業が栄えていったこと伝えており、一つの産業の発展の原点は国を越えた人の交流であることを教えてくれる。
だが、大量生産の時代を終え、工女による手作業の技術は機械生産に移り、大規模な工場は姿を消していく。このことは、我々観光業が大量輸送をベースにしたマスツーリズムの時代から、小規模なグループ、個人へと代わっていった時代の変遷と類似する。
製糸業が小規模になって求められたのは質の高さであり、人と人のつながりの深さであることだった。これは観光業も変わりはない。我々の仕事は、人との関りで生まれる手仕事。そのことに誇りを持って新年に臨みたい。
(トラベルニュースat 23年1月1日新年号)
- ロケット観光への期待(26/02/13)
- 春日大社の万灯籠(26/01/26)
- 地域を深耕できる存在に(26/01/05)
- “便乗員“より添乗員(25/12/12)
- 地元商店と一緒に誘客(25/11/27)
- 車窓越しの交流で集客(25/11/13)
- 町の本屋さんから学ぶ(25/10/28)