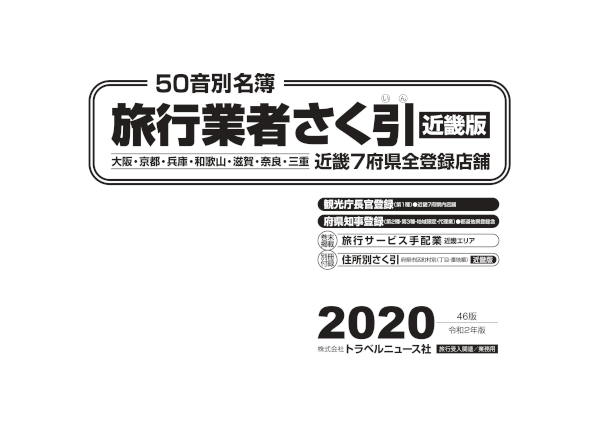サービス介助士アドバイザー談Ⅱ
アドバイザーには福祉大学に通う学生もいます。将来の夢を実現すべく、学業に向き合いながら、日常生活での困りごとやバリアとその原因を一緒に考え、サービス介助士としてどのように応対するかを対話形式で進めます。
アドバイザーの一人に「アテトーゼ型脳性麻痺」の学生がいます。何らかの原因で受けた脳の損傷によって引き起こされる運動機能の障害をさす症候群ですが、脳からの信号をうまく送受信できないために、緊張から手足が思うように動きません。今は、顎で車いすを操作しながら、学校近くで一人暮らしをしています。もちろん、自分でできないことは24時間ヘルパーを利用しています。皆さんは、どう感じますか?
フルタイムでお手伝いをお願いしてまで一人暮らしをする必要があるのか? と感じた方もいたかもしれませんね。しかし、できないことをサポートしてくれる環境が整えば、一人暮らしだってできる! 諦めることはないのです。障害があるから諦めるのではなく、どうすれば実現できるのかを考えることがこれからの社会において重要な課題であり、障害の社会モデルを考えることにつながります。社会の障壁が減ることで障害の有無に関係なく生活を楽しむことができるはずです…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2020年10月10日号)
- 中学生が考える共生社会(26/02/18)
- インクルーシブ・コミュニケーターとは?(25/12/16)
- 新たなジェロントロジーの定義と宣誓(25/11/18)
- ジェロントロジーを学び考察(25/10/17)
- ジェロントロジー総合会議@万博(25/09/18)
- 万博テーマとジェロントロジーとの共通点(25/07/17)
- お客様から教わった「おもてなし」(25/06/16)