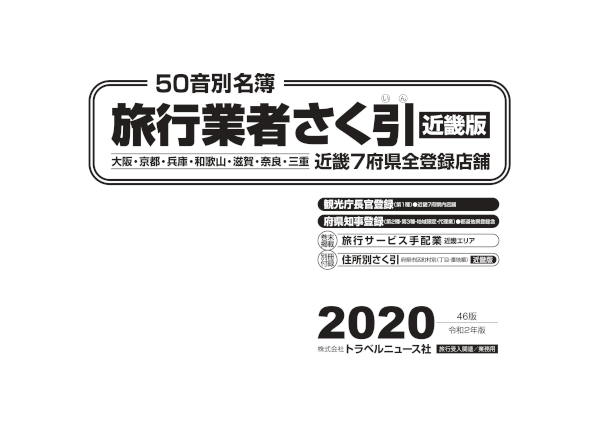中国 訪日団体旅行 期待と懸念が交錯する解禁
今月10日、中国政府は新型コロナウイルス感染症対策の一環として停止を続けていた日本への団体旅行を約3年半ぶりに解禁しました。このニュースは大手メディアも大々的に取り上げ、同日の東京株式市場では国内の航空や鉄道、小売などのインバウンド関連企業の株価が上昇するほどのインパクトがありました。
コロナ禍前の2019年、中国からの旅行者は国別訪日旅行者数最多の約3割(3188万人中959万人)、インバウンド消費額4・8兆円の約4割を占めていたこともあり、インバウンド関係者の多くは中国の団体旅行解禁を待ち望んでいたのではないでしょうか。
しかし、今後は団体旅行客が確実に増えたとしても消費額が大きく引き上がるとは言えません。なぜなら、19年の中国人訪日旅行者の66%がすでに個人旅行者であり、消費額も団体客よりも圧倒的に大きかったからです。高所得で消費額も高い中国人は個人旅行者としてすでに日本に来ています。日本政府観光局のデータでも6月の個人旅行者はコロナ禍前の同月比で約24%まで回復しました。しかも、ビジネス客として入国しながら観光を楽しむ人たちもいるので実際はもっと多いと推測されます。
また、コロナ禍の約3年間で中国の国内旅行の形態が団体旅行から個人旅行へ完全にシフトしました。現在、切符から美術館の入場券購入など、オンラインによる個人手配が基本となったため、団体旅行そのものがなくなったのです。この影響で団体客を扱う旅行会社が激減し、団体対応のノウハウを持つ人材もいなくなりました。最近では中国の景気減速が追い打ちをかけ、所得が減少したことで消費も落ちています…
(山田桂一郎=まちづくり観光研究所主席研究員)
(トラベルニュースat 2023年8月25日号)
- 26年の訪日客予測 質の向上へ転換する好機(26/01/30)
- 過去最多の訪日客 “量”の重視から政策再設計を(26/01/09)
- 台湾有事発言 民間交流こそ観光立国の礎(25/12/04)
- 日本の食を守る 観光基軸に「地産地消の経済圏」(25/11/04)
- 中小旅行会社 米国モデルにアドバイザー化(25/10/02)
- 海外予約サイト問題 “安さ”から持続可能へ試金石(25/09/04)
- 真の観光立国とは(25/08/01)