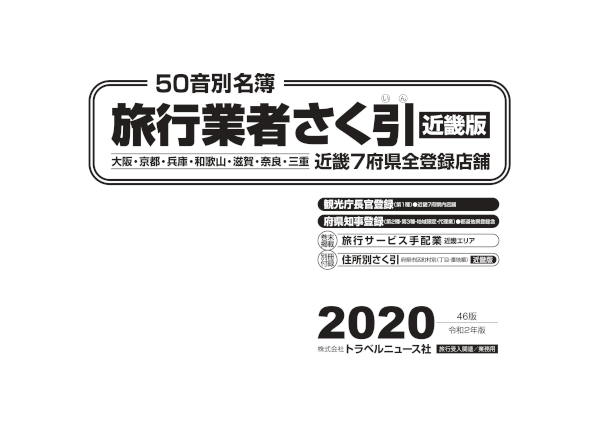日本の食を守る 観光基軸に「地産地消の経済圏」
訪日外国人旅行者の旅行目的として「日本の食を楽しむこと」は2019年以降、1位を維持しています。和食の定番である寿司や天ぷら、すき焼きからラーメンや牛丼などの大衆食に至るまで、日本の食文化は世界で評価され、ユネスコ無形文化遺産にも登録されました。世界のグルメたちからの評価としても、東京はミシュランガイドで世界最多の星付きレストランを誇り、今ではクールジャパンの象徴であるとも言えます。
一方で、ビジネスジャーナル紙が『特集・日本の「食の強み」が崩壊の兆し』として、『物流危機と一次産業の衰退により、高品質な食材供給の基盤が揺らぎ始めている。調理師免許取得者数の減少、人手不足、労働環境の厳しさが「食文化の担い手」の減少を加速させている(記事から引用)』と厳しく指摘しています。
この記事が示すように「日本の食の強み」は物流や人材等の問題によって静かに崩れ始めているのは事実だと思います。しかし、物流の効率化や労働力確保だけに頼る発想では人口減少社会が進行している日本では問題解決に限界があります。
日本食の強さを維持するためには「全国一律供給モデル」からの脱却と地域単位による「地消地産型の経済圏」の再構築が最大の課題となりそうです。食の供給を都市中心から地方分散へと転換すれば、生産者と消費者の距離が縮まり、物流負担の軽減、地域ブランドの確立により観光的価値も上昇します…
(山田桂一郎=まちづくり観光研究所主席研究員)
(トラベルニュースat 2025年10月25日号)
- 26年の訪日客予測 質の向上へ転換する好機(26/01/30)
- 過去最多の訪日客 “量”の重視から政策再設計を(26/01/09)
- 台湾有事発言 民間交流こそ観光立国の礎(25/12/04)
- 中小旅行会社 米国モデルにアドバイザー化(25/10/02)
- 海外予約サイト問題 “安さ”から持続可能へ試金石(25/09/04)
- 真の観光立国とは(25/08/01)
- 中小旅行会社の役割 観光流通インフラの再構築(25/07/01)